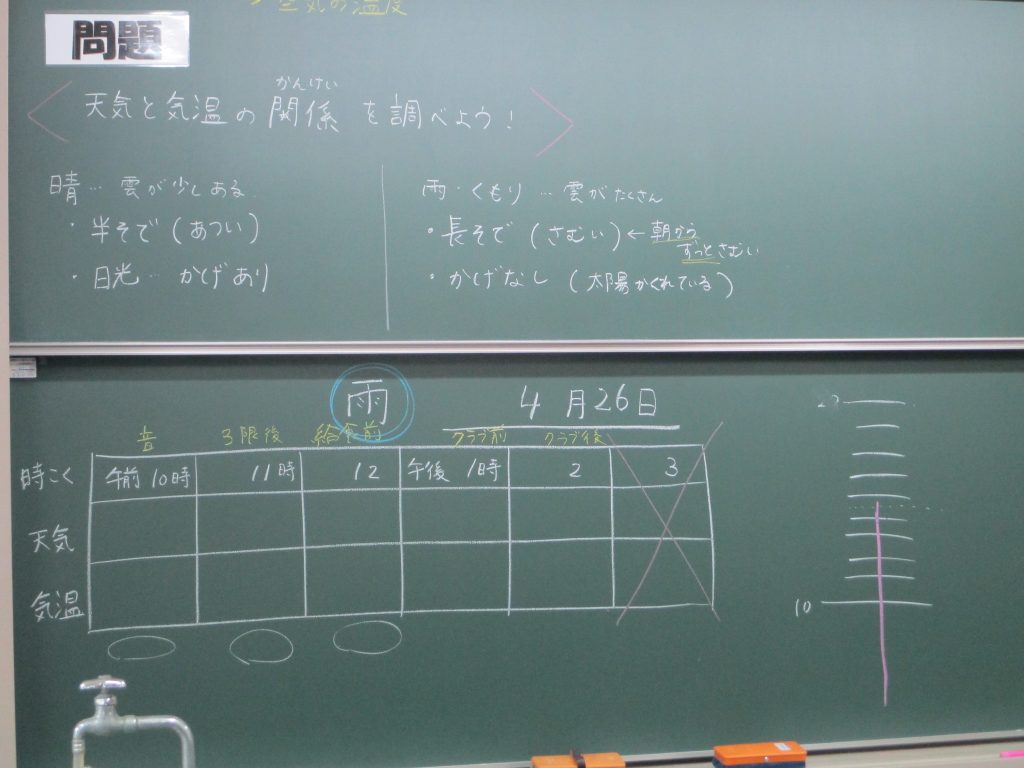5年生は、算数の時間に体積について学習しています。

算数教室のクラスは、大きな体積の表し方について、1㎥の模型を見ながら考えました。
㎥で表される体積は、単位の前につく数値がc㎥を使って表したときよりも小さくなることから、児童の量感にずれが生じることがあります。
実際の体積を示すことで、数値は小さくなっても、体積は大きくなっているということを実感させるようにしています。

教室で学習しているクラスでは、考えをまとめたノートを示しながら、自分がどのような筋道で答えを導きだしたのかを説明し合っていました。
根拠を示しながら筋道を立てて考えを説明する力は、算数科に限らず多くの教科で生かせる力です。
このような意見交流の場を意図的に設定し、力を高められるよう、授業を展開を考えています。